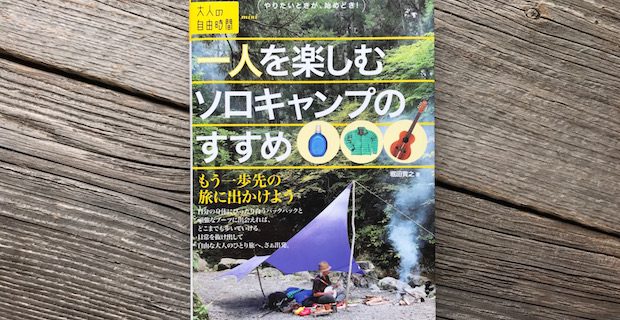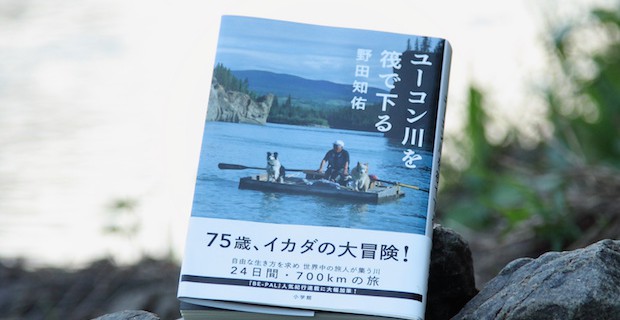- カルチャー
【ユーさんの72年_2】中川祐二、72年目のアウトドアノート〜アウトドアに目覚める ── 其の壱
2020.04.29 Wed
中川祐二 物書き・フォトグラファー
いったいいつ、このようなおもろしいことを知ってしまったのだろうか? もちろん、僕が子どものころはアウトドアなんという言葉は日本にはなかった。
僕の生まれたのは都心から10分ほどのところだが、当時は麦畑があり、原っぱがあり、野球をしたりレンガで作ったトラップでスズメを捕って遊んだりした。そばを流れる玉川上水に落ちたこともあった。
小学校の4年生のとき、親父に連れられ東京湾へハゼ釣りに行った。いま考えると、これがアウトドア好きになった始まりかもしれない。いまでもハゼ釣りはいちばん楽しい釣りのひとつ。そんなことから、のちの茨城県大洗町でのアウトドア教室「アイアンキッズ」(*1)活動でも欠かすことのできない楽しみとなった。
(*1)アイアンキッズ=後年、茨城県大洗町の主催する子どものためのアウトドア教室「アイアンキッズ少年海賊隊」の講師を務めた際にも幼少時のハゼ釣り体験は大いに活かされることに。
毎年10月10日は中川家のハゼ釣りの日と決まっていた。親父がハゼ釣りの好きな親戚の叔父たちと僕たちを連れ東京湾へ出かけた。浜松町から歩き金杉橋の「縄安」という船宿が贔屓だった。隣がうちの遠い親戚だったせいもある。佐野さんという若い船頭が付いてくれた。
当時の船は10人乗りくらいの焼き玉エンジン(*2)の木造船。まだ東京湾に海苔シビ(*3)が立てられていたころで、その間を櫓で練って船の流れを調節しながら釣った。
(*2)焼き玉エンジン=「焼き玉」とは「焼き玉機関」の略称。シリンダーヘッドを熱し、ここに軽油を噴射して爆発を起こす。これによってピストン運動を得る内燃機関のこと。(*3)海苔シビ=海苔養殖のため網を張った竹の杭。
昼近くになると、波の来ない安全なところに船をもやい、天ぷらの支度をした。船頭が作るこの天ぷらがうまい。ハゼ、メゴチ、エビをごま油で揚げ、大根おろし、しょうがの効いた天つゆでいただく。ほかにはアサリのおつけ(*4)、キュウリとダイコンのお香香(*5)、そしておひつに入ったごはん。その後、自分たちで野菜を持ち込み、精進揚げをつくってもらったこともあった。
(*4)(*5)おつけ、お香香=おつけは「お汁」、おみおつけの略。お香香は「おこうこう」。つまり、漬物、香の物の略。どちらも下町言葉。
天ぷらにする魚は釣ったものではなく、船頭があらかじめ用意してあるものだ。われわれが釣ったハゼをあてにしていると、いつまでたってもお昼にはならない。
午後はまた釣れそうな場所を移動しながら釣った。当時は、船の大型化が始まったころだが、佐野さんの和船は小さく、ほかの船が入れないようなところをくぐって行くこともあった。それも干潮が始まるころにくぐり、満潮の前に出てこないと閉じこめられてしまうようなところだった。
そこはいま考えると首都高の橋脚をくぐった、大井競馬場との間にできたほんの20メーター幅くらいの水路。浅いところだったがよく釣れた覚えがある。
またあるときは木場の貯木場に入って釣ったこともあった。船を杭にもやい、船から降りて浮いている大きな木を渡りながら釣った。誰かが落ちたこともあった。この貯木場、ハゼの釣り場としては超一級の釣り場だったが、誰のときだったか、ヨットの好きな知事が僕たちの反対を押し切って埋め立ててしまった。
あるとき、船頭の佐野さんがエンジンのスロットルを上げ僕を呼んだ。
「若旦那、舵とって下さい。あそこの煙突に向かって!」
と操船を任された。何とも気持ちがいいではないですか。江戸前の釣り船の船頭に”若旦那"と呼ばれ、まるで落語『船徳』(*6)の徳兵衛のような心持ちだ。もっとも徳兵衛は放蕩が過ぎ、船宿に居候を決め込んだ若旦那だが。
(*6)船徳=古典落語の演目のひとつ。初代の古今亭志ん生が作った。八代目桂文楽の十八番。
1日6、7時間ほどで僕は300匹くらい釣った。親父もそのくらい釣っている。家へ帰ると風呂場にこもり、鱗を落としハラワタを出し、天ぷらができるようにさばいた。ふたりでやっても夜中の2時、3時までかかった。
この中川家のハゼ釣りイベントは、中川一族に加わるための通過儀礼でもあった。つまり、息子や娘、孫の結婚が決まると、嫁さん婿さんはこの釣り大会に参加し、お披露目をするということになっていた。
 「江戸前天ぷら付きハゼ釣り」のお昼の風景。これは10年ほど前の写真で、船は大型化しグラスファイバーになったが基本的にはむかしと変わらない。持ち込んだビールを飲みながら天ぷらの揚がるのを待つ。竿を出したままにしておくとこの間にも釣れることがある。みんなから非難ごうごうとなること必至。久しぶりに一族や友人と過ごす楽しいひとときだ。
「江戸前天ぷら付きハゼ釣り」のお昼の風景。これは10年ほど前の写真で、船は大型化しグラスファイバーになったが基本的にはむかしと変わらない。持ち込んだビールを飲みながら天ぷらの揚がるのを待つ。竿を出したままにしておくとこの間にも釣れることがある。みんなから非難ごうごうとなること必至。久しぶりに一族や友人と過ごす楽しいひとときだ。
叔父の奥さんが乗ったときのことだった。船頭が、「はい、竿をあげて!」とみなに声をかけ船を動かした。しばらく走ると今度はスピードを落とし「みんな前を向いて!」と。何をするのかとみながきょとんとしていると、叔母に船のともにこいと指示をした。その当時、小さな船にはトイレが付いていない。男たちは船のともに行き大海と青空に向かって放水するのだが、女性はそうはいかない。これは船頭の女性に対する最大のリスペクトだった。
つまり、釣り師紳士諸君は前方を見ているので、その間に小用を済ませろということだった。しかし、そういわれても揺れる船の上で用を足すというのはなかなかできるものではない。とくにこの叔母は潔癖性で急にそんなことを言われ困っていた。すると船頭、今度は船を陸に向かって走らせ、こんもりと緑に覆われた島に着けた。この島に上陸しそこで用を済ませろと。ここは無人島だから大丈夫だと説明した。そこはいま、テレビ局などが建つお台場だった。
トイレ話をもうひとつ。この江戸前のハゼ釣り船、当時トイレはまったく付いていなかった。仕立てて仲間で乗るときは船内の移動は楽だったが、乗り合いとなるとなかなかこれがむずかしい。狭い船内を動くと常連のジイサンたちにいやな顔をされたものだった。では、どうするかというと船には専用の器具が用意されている。50センチほどの節を抜いた竹筒に紐の取っ手を付けたものだ。自分の釣り座に立ち、この筒にわがものを入れ放水する。落としてはいけないので、紐をしっかりと握りながらである。使い終わると海の水で洗い次の人へ。ちょっと気持ち悪かった。
揺れる船の中、これでは年寄りには危ない。そこで次ぎの兵器は琺瑯(*7)のコップになった。かなり大きく容量はたっぷりあった。座ったままこれに放水し海へ。しかし、座ったまま致すというのはこれもなかなかむずかしかった。
(*7)琺瑯=ほうろう、ホーロー。ガラス質のうわぐすりを表面に焼き付けたもの。琺瑯引き。
佐野さんの船は木造で、ところどころ銅の化粧板が付いた風情のある江戸前の船だった。移動するときは波しぶきをよける板を付け、釣るときはこれを外す。外した板、小さな専用の柱は自分の釣り座の前に整理してしまう。竿掛けを付ける。このときもねじで締め付けるため、船に傷がつかないように木切れをはさむ人もいた。エサ箱を付け、船頭が用意したエサのゴカイが弱らないよう、またつかみやすいように砂を持ってくる人もいた。
中通しの竹竿をつなぎ、長短2本をセットするまでの所作がベテランとなるとこれが恰好いい。何度も通い、”月謝"を払わないとなかなかそうはできなかった。
 竿掛けとエサ箱を船にセットし、竿を掛ける。この竿掛けは木製のかなり古いもの。僕が初めてハゼの船に乗ったとき親父から与えられたもの。当時は古くて恥ずかしかったが、手入れをしていまでも使っている。竿は竹竿。この釣りだけはグラスやカーボンではだめだ。長さの違う和竿を数本持っていき、虫干しを兼ねてみんな出して使うことにしている。
竿掛けとエサ箱を船にセットし、竿を掛ける。この竿掛けは木製のかなり古いもの。僕が初めてハゼの船に乗ったとき親父から与えられたもの。当時は古くて恥ずかしかったが、手入れをしていまでも使っている。竿は竹竿。この釣りだけはグラスやカーボンではだめだ。長さの違う和竿を数本持っていき、虫干しを兼ねてみんな出して使うことにしている。
ある日、船が隅田川を走っていたとき、大伯父が僕を呼び寄せ耳のそばで話し始めた。この大伯父は、がんで手術したとき声帯も取ってしまったため、声がほとんど出なかった。
ちょうど船は柳橋辺りを走っていた。コンクリの堤防の向こう側にいかにもというようなしゃれた料亭が見えた。すると大伯父はかすれた小さい声を振り絞るように言った。
「むかし、ああいう料亭に行ってな、朝になると敷島というタバコに十円札を丸めて入れたものをそっと渡してくれたもんだよ。敷島と十円札が同じ幅だったんだな」
嫌な思い出もある。釣りが終わり船宿がある河岸に船をもやった。僕は自分の荷物を片付け、まわりのゴミを拾って持ち帰ろうとしていた。すると船頭が、「若旦那、いいよ、ゴミはあたしが捨てとくからそのままにしな」と。
僕はそれならとゴミをそのままにして船を降りた。一日中揺れる船に乗っていたせいで、陸に上がってもまだ揺れているような "陸酔い"がしていた。
バタバタという音がしたので振り返った。船頭がさっき僕がゴミを集めておいたゴザをバタバタと払っていた。ビニール袋や空き缶が海に漂っていた。やっぱりまとめて持ってくればよかったと思ったがもう遅かった。ちょっとショックで船頭にも何も言えなかった。いまでもその光景が焼き付き、後悔している。
親父が亡くなって僕がハゼ釣りイベントを引き継いだ。しばらくして佐野船頭が引退するという。あちらこちらと船宿を替えてみたが、彼ほどうまい天ぷらを揚げてくれる船頭が見つからず、「江戸前天ぷら付きハゼ釣り」は終わった。
親父とは川へも釣りに出かけた。はじめは京王多摩川だった。僕が小学生のころの河原は、まるで海水浴場のようだった。河原にはよしず張りの海の家ならぬ川の家があった。僕たちは家族で出かけ、シートを敷きお弁当を広げ川で水浴びをした。
ここで親父に教わったのは「あんま釣り」だ。いまこの言葉は差別用語となっていて使えないのだが、その動作から「ピストン釣り」と言い換えているようだ。道具は1メーターほどの竿を使う。仕掛けは、竿よりちょっと長めの糸に小さい鈎を付けただけの簡単なもの。釣り方は川の下流に向かって立ち、竿を水中に入れそれを前後に動かしながら釣る。遠くから見るとあんまさんが杖をついているように見えるからこう呼んだのだと思う。そう見ると「ピストン釣り」もその動作から名付けたのだろうが、言い得て妙である。
エサは石の裏にいるチョロ虫(*8)。これを付け竿を前後に動かす。魚が食い付かなければ足で川の石を動かしながら上流側へ後ずさりする。石を動かし、その石に付いているチョロ虫を流すことでコマセ(*9)効果が生まれるのだと思う。
(*8)(*9)チョロ虫、コマセ=チョロ虫はカゲロウの幼虫。コマセは撒き餌のこと。
自分が川に入っていることで生まれる川の淀み、そこに動くエサが流れる。魚はすぐに食いついた。釣れる魚はハヤ(*10)やヤマベ(*11)だ。
(*10)(*11)ハヤ、ヤマベ=ハヤはウグイ、ヤマベはオイカワ。
親父は捕まえたチョロ虫を軽くつぶし肩に張り付けていた。エサがなくなったらすぐに使えるようにエサ箱のかわりだ。足はいつも半わらじというかかとのない小さなわらじを履いていた。足半(アシナカ)とも言うらしい。どうしてこれを履いていたのかは知らなかったが、僕も親父と同じ格好をして釣った。おもしろいように釣れた。
京王多摩川のさらに上流、是政へも行った。親父は「蚊ばり釣り」(*11)が好きだった。まるで蚊のような小さな毛ばりを5、6本付け、菱形の浮子で流れに逆らいながら流して釣る。魚がかかるとその魚信(*12)が直接手に伝わる。子どもにとって心臓がドキドキする瞬間だ。そしてキラキラした魚が釣れてくる。1回に2匹も3匹もかかることがある。
(*11)蚊ばり釣り=「蚊ばり」とは「蚊鉤」のこと。羽毛などを使って蚊に似せてつくった擬餌鉤で、水面を飛ぶ虫を捕食する習性を持つ魚を釣るときに用いる。(*12)魚信=魚がエサをつつくことで、竿先などに伝わってくる感触のこと。
このときは、釣りがそれほど好きではない兄には声をかけず、次男の僕を誘った。当時、着るものが潤沢にある訳ではなく、親父は軍隊で使っていた乗馬ズボンにゲートルを巻いていた。僕も同じような格好をさせられた。釣り竿を持ち、ザックを背負い京王線に乗った。はたで見るとおもしろい風景だったにちがいない。
どうやって川へアクセスしたかはまったく覚えていない。このあたりの多摩川は川幅が広く、川は河原の中を何本かに分かれ流れていた。釣り場はチャラ瀬(*13)ではなく、トロ場(*14)でもない、中くらいの強さで膝下あたりの深さの流れが釣りやすい。そんな流れを探し釣り歩いた。
(*13)(*14)チャラ瀬、トロ場=チャラ瀬は「浅くチャラチャラとした流れ」、トロ場は「ゆったりと表面が波立たない流れ」のこと。
 多摩川は、その水源の山梨から神奈川、東京へと138キロを流れる都会にありながら自然豊かな川。上流部ではヤマメ、イワナなどの渓流魚。中流域ではアユ、オイカワ、ウグイ。下流域ではコイ、マルタ、ハゼなどが生息し、都会の釣りファンにはありがたい川だ。最近は飼いきれなくなった魚を放す人が増え「タマゾン川」と揶揄する人もいる。
多摩川は、その水源の山梨から神奈川、東京へと138キロを流れる都会にありながら自然豊かな川。上流部ではヤマメ、イワナなどの渓流魚。中流域ではアユ、オイカワ、ウグイ。下流域ではコイ、マルタ、ハゼなどが生息し、都会の釣りファンにはありがたい川だ。最近は飼いきれなくなった魚を放す人が増え「タマゾン川」と揶揄する人もいる。
遠くに川に立ちこむ親父の姿は見えていた。そろそろまわりは薄暗くなり、帰る時間かなと思うのだが、親父はいっこうに動く気配はないばかりか、まめに竿を動かしている。釣れているようだ。僕の竿も小気味よいアタリが続いていた。
まわりは真っ暗になり月が出てきた。親父が立ちこんでいる場所はさっきとまったく変わっていない。水面に映った親父のシルエットは相変わらずこまめに竿を動かしていた。
ようやく川から上がってきた親父の魚籠は魚で一杯になっていた。真っ暗な中では道具を仕舞えないので、そのままの格好で夜道を駅まで歩いた。歩くたびに靴はぶちゅぶちゅという音を立てた。親父のぶちゅぶちゅという音を頼りに田んぼのあぜ道を歩いた。
駅の待合室、裸電球の下で道具を仕舞い、竿を畳んだ。僕のゲートルはゆるみ足首にずり落ちていた。濡れた足のまま電車に乗った。魚がいっぱい入った魚籠を持った変な格好をした親子。みなにじろじろと見られた。電車の床は魚籠からこぼれた水が絵を書いていた。
ちょっと大きくなると多摩川は、僕の釣りのテリトリーを大いに広げてくれた。西調布、当時は「上石原」という駅名だった。ここから南へ一本道を歩く。途中、映画の撮影所のようなものがあり、さらに行くと右側にバラックのような店が1軒あった。ここで蒸かした芋を売っていた。確かメリケン粉(*15)の小袋が付いて10円だった記憶がある。これにさなぎ粉を混ぜよく練って魚釣りのエサにした。
(*15)メリケン粉=小麦粉のこと。
さらに進むと薮の向こうに幾つもの池が見える。ここは砂利を採掘したあとに水が溜まった砂利穴である。大きな蟻地獄に水が溜まったようなもので、これに落ち命を落とした子どももいたという。ここに小魚がいっぱいいた。ハヤ、ヤマベ、いちばんの狙いはクチボソ(*16)だった。毎回仕掛けを工夫し、日曜ごとに出かけた。そのうち砂利穴で出会う友だちもできた。
(*16)クチボソ=モツゴのこと。
砂利穴から土手に上がるとそこは広々とした多摩川だ。冬のことだった。流れで釣りをしている大人の人がいい型のハヤを何匹も釣っていた。そばへ行って聞いてみた。するとその人はエサに豚のレバーを使っているという。小さく切ったレバーだけではすぐに外れてしまうので、付けたレバーを真綿で数回巻いていた。
おばあちゃんに言って真綿を少しもらい、お袋にレバーを買ってもらい川へ行った。あのときの大人の人のやり方を思い出しながらやってみた。ちっとも釣れなかった。一日やってもうエサのレバーがなくなるころ、浮子がびくんと沈んだ。思い切って合わせた。糸がピンと張り右左へと動き回った。しばらくしてようやく岸に寄ってきたのは20センチを超えたオレンジ色の婚姻色(*17)が鮮やかなハヤだった。
(*17)婚姻色=とくに繁殖期に現れる、独特な体の色や斑紋のこと。
1日に20匹を釣ったら新しい竿を買ってくれるという約束を親父から取り付け、砂利穴へと通った。ある日、帰ろうとしたら帰りの電車賃がないことに気が付いた。どこかで落としてしまったのだろう。困った。仕方なく調布まで歩き交番のお巡りさんに頼み込んだ。よくは覚えていないが説教をされた。そのとき『太公望』(*18)の話を聞いた。よくわからない話だと思った。うちへ電話され、帰りの電車賃数十円を借りて帰ってきた。
(*18)太公望=古代中国、斉の初代公「呂尚」のこと。周の文王が渭水のほとりで釣りをしてい呂尚をみて「これが先君大公が待ち望んだ賢人である」といったという逸話から「釣り好き」をさす。
翌週、借りたお金を持って調布まで返しに行った。その後、砂利穴へ行ったという記憶はない。
 東京湾に海苔シビがあった頃は海で釣ったが、最近は早い時期ならば川の中で釣ることが多くなった。ハゼは6月頃から川で釣れ始め、10月頃がいちばんのシーズン。寒さが厳しくなる12月にも行ったことがある。船頭はこたつを用意してくれた。冬は深場での釣りになるため、長い竿は使いづらく60センチほどの「水雷」という竿を使った。飴色になった20センチオーバーのハゼが釣れた。今はその水雷を使う場所がない。あー、昔はよかったな。
東京湾に海苔シビがあった頃は海で釣ったが、最近は早い時期ならば川の中で釣ることが多くなった。ハゼは6月頃から川で釣れ始め、10月頃がいちばんのシーズン。寒さが厳しくなる12月にも行ったことがある。船頭はこたつを用意してくれた。冬は深場での釣りになるため、長い竿は使いづらく60センチほどの「水雷」という竿を使った。飴色になった20センチオーバーのハゼが釣れた。今はその水雷を使う場所がない。あー、昔はよかったな。